貝毒とは何か
貝毒はホタテやカキなどの二枚貝が餌として有毒プランクトンを食べることで毒素を一時的に
蓄積し、これを食べた人が中毒症状を起こす現象を呼ぶ。食用となる二枚貝自身には毒素を
作り出す能力はない。日本で問題となる貝毒には有毒プランクトンの種類によって麻痺性貝毒
と下痢性貝毒の2種類がある。これ以外にも多種類の貝毒が知られている(1−3参照)。
蓄積し、これを食べた人が中毒症状を起こす現象を呼ぶ。食用となる二枚貝自身には毒素を
作り出す能力はない。日本で問題となる貝毒には有毒プランクトンの種類によって麻痺性貝毒
と下痢性貝毒の2種類がある。これ以外にも多種類の貝毒が知られている(1−3参照)。
貝類の食中毒件数としては、生食等によるビブリオ腸炎やノロウィルス(SRSV)による中毒
事例が圧倒的に多く、貝毒による中毒は全体の10%以下と少数である。しかしながら、貝毒は
加熱によって毒性がほとんど失われず、汚染された二枚貝は流通管理を徹底しても毒性は低
下しない。さらに麻痺性貝毒のように、食後30分程度で発症し、治療薬もないことから、致死量
以上の摂取で死亡してしまう例もある。従って発生件数が少ないからといって軽んじることはで
きない。
事例が圧倒的に多く、貝毒による中毒は全体の10%以下と少数である。しかしながら、貝毒は
加熱によって毒性がほとんど失われず、汚染された二枚貝は流通管理を徹底しても毒性は低
下しない。さらに麻痺性貝毒のように、食後30分程度で発症し、治療薬もないことから、致死量
以上の摂取で死亡してしまう例もある。従って発生件数が少ないからといって軽んじることはで
きない。
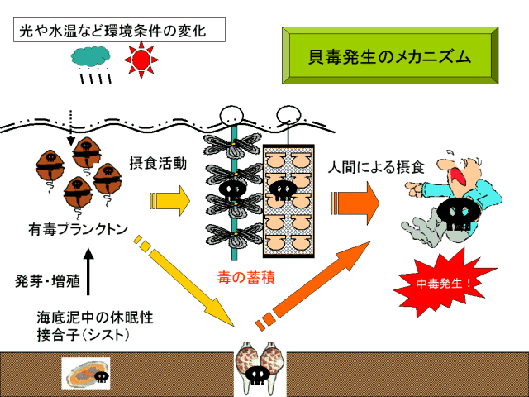
1 麻痺性貝毒(Paralytic Shellfish Poisoning = PSP)
原因となる有毒プランクトン
アレキサンドリウム タマレンセ(Alexandrium tamarense, 渦鞭毛藻)
アレキサンドリウム カテネラ (Alexandrium catenella, 渦鞭毛藻)
アレキサンドリウム タミヤバニチ(Alexandrium tamiyavanichii, 渦鞭毛藻)
ギムノディニウム カテナータム (Gymnodinium catenatum, 渦鞭毛藻)
日本沿岸で発生する麻痺性貝毒は以上4種のいずれかを原因とする。地域・季節などによっ
て発生する種類が異なり、希にこれらが同時に混合して発生することもある。 アレキサンドリ
ウム属については、さらに数種の有毒種の存在が知られているが、今のところ日本沿岸で麻
痺性貝毒を引き起こした事例は報告されていない。
て発生する種類が異なり、希にこれらが同時に混合して発生することもある。 アレキサンドリ
ウム属については、さらに数種の有毒種の存在が知られているが、今のところ日本沿岸で麻
痺性貝毒を引き起こした事例は報告されていない。
毒 性
いずれの種類もアルカロイドの一種である毒素を産生する。毒素はサキシトキシンを基本骨
格とし、さらに30種類の誘導体の存在が知られている。有毒プランクトンの細胞内毒素はプロ
トゴニオトキシン(PXあるいはC-toxin)、ゴニオトキシン(GTX)を主成分とし、サキシトキシン
(STX)やネオサキシトキシン(neoSTX)を副成分とする。いずれも低分子、水溶性で熱に強い
天然毒である。最も毒性が強いSTXの経口毒性は猛毒のサリンと同程度である。これらはフ
グ毒のテトロドトキシン同様、ナトリウムチャンネルの特異的ブロッカーとして知られている。
格とし、さらに30種類の誘導体の存在が知られている。有毒プランクトンの細胞内毒素はプロ
トゴニオトキシン(PXあるいはC-toxin)、ゴニオトキシン(GTX)を主成分とし、サキシトキシン
(STX)やネオサキシトキシン(neoSTX)を副成分とする。いずれも低分子、水溶性で熱に強い
天然毒である。最も毒性が強いSTXの経口毒性は猛毒のサリンと同程度である。これらはフ
グ毒のテトロドトキシン同様、ナトリウムチャンネルの特異的ブロッカーとして知られている。
毒化する貝
ホタテガイ、マガキ、アサリ、ヒオウギガイ、アカガイ、ムラサキイガイ、アカザラガイなど種々
の二枚貝が毒化する。マボヤなども毒化することが知られている。さらに、毒化した二枚貝を
捕食した肉食性の巻貝、あるいはカニの毒化例も知られている。
の二枚貝が毒化する。マボヤなども毒化することが知られている。さらに、毒化した二枚貝を
捕食した肉食性の巻貝、あるいはカニの毒化例も知られている。
症 状
通常食後10〜30分で唇、舌、顔面などがしびれ、手足の発熱感がはじまり、重傷の場合は
運動失調や呼吸困難を起こす。毒素は食後数時間以上経過すると体外に排泄される。過去
に多数の死亡例有り。
運動失調や呼吸困難を起こす。毒素は食後数時間以上経過すると体外に排泄される。過去
に多数の死亡例有り。
対 応
治療薬は開発されていない。対症療法として、胃洗浄、点滴、人工呼吸。フグ毒中毒患者の
治療に準ずる。
治療に準ずる。
特記事項
現在日本で最も発生頻度の高い貝毒である。
2 下痢性貝毒(Diarrhetic Shellfish Poisoning = DSP)
原因と考えられるプランクトン
ディノフィシス フォルティー(Dinophysis fortii, 渦鞭毛藻)
ディノフィシス アキュミナータ(Dinophysis acuminata, 渦鞭毛藻)
ディノフィシス ノルベチカ(Dinophysis norvegica, 渦鞭毛藻)
ディノフィシス アキュータ(Dinophysis acuta, 渦鞭毛藻)
日本沿岸では主に前3種が出現。これ以外のディノフィシス属でも下痢性貝毒の産生が疑わ
れているがはっきりしない。
れているがはっきりしない。
毒 性
原因となる毒素はオカダ酸(OA)、ジノフィシストキシン(DTX)、ペクテノトキシン(PTX)、イェッ
ソトキシン(YTX)などのポリエーテル化合物で、それぞれに多種類の誘導体の存在が知られ
ている。PTXとYTXについては近年下痢原性を示さず経口毒性も著しく低いことから、下痢性
貝毒とは区別し、脂溶性貝毒(Lipophlic Toxin)として取り扱われつつある。
ソトキシン(YTX)などのポリエーテル化合物で、それぞれに多種類の誘導体の存在が知られ
ている。PTXとYTXについては近年下痢原性を示さず経口毒性も著しく低いことから、下痢性
貝毒とは区別し、脂溶性貝毒(Lipophlic Toxin)として取り扱われつつある。
毒化する貝
ホタテガイ、ムラサキイガイ、アサリ、アカザラガイ、コタマガイ、チョウセンハマグリなどの二
枚貝全般。
枚貝全般。
症 状
下痢性貝毒であるOAやDTXなどの毒素は、腸管において特異的な細胞毒性を示し、粘膜の
浮腫を伴う生理的傷害を与える。これによって強烈な下痢原性を示す。通常食後4時間以内
で発症し、下痢(必発)、吐気、腹痛などの消化器系の症状を主体とする。食後の発症が短時
間で発生すること、加熱調理された食材でも発症することなどから、発症例の多い病原微生物
を原因とする食中毒と簡易に区別する場合のポイントである。ほぼ3日間で回復し、予後は良
好で死亡例はない。ただ毒素がタンパク質のリン酸化を強く阻害するので、発ガン性の疑いが
指摘されている。低濃度摂取を続けた時の慢性毒性について知見は乏しい。
浮腫を伴う生理的傷害を与える。これによって強烈な下痢原性を示す。通常食後4時間以内
で発症し、下痢(必発)、吐気、腹痛などの消化器系の症状を主体とする。食後の発症が短時
間で発生すること、加熱調理された食材でも発症することなどから、発症例の多い病原微生物
を原因とする食中毒と簡易に区別する場合のポイントである。ほぼ3日間で回復し、予後は良
好で死亡例はない。ただ毒素がタンパク質のリン酸化を強く阻害するので、発ガン性の疑いが
指摘されている。低濃度摂取を続けた時の慢性毒性について知見は乏しい。
特記事項
ほ乳類に対して下痢性を示さないが、マウスへの腹腔内投与で致死活性を示す下痢性貝毒
成分としてイェッソトキシン(YTX)が知られている。原因生物としてはプロトケラチウム レティ
キュラータム(Protoceratium reticulatum)などが報告されている。経口毒性がないため食品衛
生上は問題とならないが、現在のマウス試験法では疑似陽性の原因となる。
成分としてイェッソトキシン(YTX)が知られている。原因生物としてはプロトケラチウム レティ
キュラータム(Protoceratium reticulatum)などが報告されている。経口毒性がないため食品衛
生上は問題とならないが、現在のマウス試験法では疑似陽性の原因となる。
3 その他の貝毒
記憶喪失性貝毒(ASP)
脳のシナプスに傷害を与える神経毒ドウモイ酸(domoic acid, アミノ酸の一種)による中毒。
1992年にカナダで大規模な中毒事件が発生し、3名の死亡者が出た。原因種はドウモイ酸を
産生する珪藻Pseudo-nitzschia属によるものである。日本にもこれらの有毒珪藻が分布してお
り、過去に一斉調査が実施されたものの、検出される毒素の量は規制値と比較しても極端に
低く、中毒発生のリスクは高くないとしてモニタリングは実施されていない。ドウモイ酸は古くか
ら南西諸島で虫下しとして利用されていた紅藻ハナヤギの殺虫成分として知られていた。
1992年にカナダで大規模な中毒事件が発生し、3名の死亡者が出た。原因種はドウモイ酸を
産生する珪藻Pseudo-nitzschia属によるものである。日本にもこれらの有毒珪藻が分布してお
り、過去に一斉調査が実施されたものの、検出される毒素の量は規制値と比較しても極端に
低く、中毒発生のリスクは高くないとしてモニタリングは実施されていない。ドウモイ酸は古くか
ら南西諸島で虫下しとして利用されていた紅藻ハナヤギの殺虫成分として知られていた。
シガテラ(原因毒はシガトキシンやマイトトキシン)
ポリエーテル化合物であるシガトキシンやマイトトキシンを原因とする中毒。アオブダイ、オニ
カマスなど南方系の魚類を食することで発症する。原因種はGambierdiscus属などの底生性渦
鞭毛藻で、これら有毒渦鞭毛藻が付着した海藻類を草食性魚類が捕食することで毒が魚に蓄
積する。
カマスなど南方系の魚類を食することで発症する。原因種はGambierdiscus属などの底生性渦
鞭毛藻で、これら有毒渦鞭毛藻が付着した海藻類を草食性魚類が捕食することで毒が魚に蓄
積する。
沖縄や太平洋側で散発的な中毒事例がある。生死には問題はないが、ドライアイスセンショ
ションと呼ばれる温度感覚の逆転現象(温水シャワーなどを浴びると氷水を浴びさせられたよ
うなショックを受ける)が数ヶ月以上継続するなど深刻である。
ションと呼ばれる温度感覚の逆転現象(温水シャワーなどを浴びると氷水を浴びさせられたよ
うなショックを受ける)が数ヶ月以上継続するなど深刻である。
シガテラ様中毒
従来南方系の魚類を食することで発症する中毒は一括してシガテラ中毒として取り扱われて
いたが、中毒を引き起こした患者の症状からいわゆる別の毒素の存在も示唆されていた。
いたが、中毒を引き起こした患者の症状からいわゆる別の毒素の存在も示唆されていた。
近年アオブダイやイシガキダイなどを原因とする食中毒が散発的に発生し、ポリエーテル化
合物のパリトキシンが原因物質として疑われている。原因生物として、底生性渦鞭毛藻の
Osteropsis属が疑われている。近年南方魚類の本土側への分布拡大に伴い、食中毒事件が
散見されるようになっている。
合物のパリトキシンが原因物質として疑われている。原因生物として、底生性渦鞭毛藻の
Osteropsis属が疑われている。近年南方魚類の本土側への分布拡大に伴い、食中毒事件が
散見されるようになっている。
アザスピロ酸中毒(AZP)
神経毒の一種であるアザスピロ酸を原因とする中毒。1995年にアイルランドで養殖されてい
たムラサキイガイが原因で下痢、腹痛などの集団食中毒患者が発生した。原因種は渦鞭毛藻
Protoperidinium属が疑われている。本邦での中毒事例は無いが、今後モニタリング体勢の充
実が望まれる。
たムラサキイガイが原因で下痢、腹痛などの集団食中毒患者が発生した。原因種は渦鞭毛藻
Protoperidinium属が疑われている。本邦での中毒事例は無いが、今後モニタリング体勢の充
実が望まれる。
神経性貝毒(NSP、原因毒はブレーベトキシンやジムノジミン)
ポリエーテル化合物であるブレーベトキシンとその類縁体を原因とする中毒。
4 毒力(毒性)の表示について
日本においては貝毒の単位としてMU/g(マウスユニット/グラム)を用いている。例えば麻痺
性貝毒の場合、1MUとは体重20gのマウスが15分で死ぬ量と規定されている。食品衛生法第4
条により麻痺性貝毒の場合、1グラム当たり4マウスユニットを超えるものは人の健康を損なう
恐れがある食品として販売等をしてはならないとされている。下痢性貝毒は可食部で 0.05MU/
g以上の場合、同様に販売等をしてはならない。
性貝毒の場合、1MUとは体重20gのマウスが15分で死ぬ量と規定されている。食品衛生法第4
条により麻痺性貝毒の場合、1グラム当たり4マウスユニットを超えるものは人の健康を損なう
恐れがある食品として販売等をしてはならないとされている。下痢性貝毒は可食部で 0.05MU/
g以上の場合、同様に販売等をしてはならない。
麻痺性貝毒の場合、人に対する致死量(体重60Kg)は3,000〜20,000マウスユニットといわれ
ている。4マウスユニット/グラムのカキ(内重量15gと仮定)では、50〜340個分にあたる。 希
に100MU/g以上に毒化することもあり、この場合数個の二枚貝を食べるだけで致死量に達す
ることもある。
ている。4マウスユニット/グラムのカキ(内重量15gと仮定)では、50〜340個分にあたる。 希
に100MU/g以上に毒化することもあり、この場合数個の二枚貝を食べるだけで致死量に達す
ることもある。
通常天然毒や化学物質で汚染された食品の毒性は、原因となる毒素の含量(湿重量あたり
のグラム数あるいはモル濃度)を基準として規制値が設けられ、これらを基に主に機器分析等
でモニタリングが実施される。しかし、貝毒の場合は前述のようにマウスユニットという、生物検
定で求められた数字を規制値として採用している。
のグラム数あるいはモル濃度)を基準として規制値が設けられ、これらを基に主に機器分析等
でモニタリングが実施される。しかし、貝毒の場合は前述のようにマウスユニットという、生物検
定で求められた数字を規制値として採用している。
5 貝毒の発生環境について
貝毒の原因となる有毒プランクトンは一年のうちでごく限られた時期にのみ出現する。非発
生時期はシスト(休眠胞子)の状態で海底に存在している。水温が適当になると目を覚まして
栄養細胞として増殖し、カキ、アサリ、ムラサキイガイなどの二枚貝が栄養細胞を餌として体内
に取り込み毒化する。アレキサンドリウム属の一部では現場水温が発生を知る良い指標とな
るが、ギムノディニウム カテナータムは真夏から真冬まで発生するので水温による予測が困
難である。また下痢性貝毒の原因プランクトンはシストを形成しないため、専ら栄養細胞のモ
ニタリングによって貝毒発生を予測せねばならない。
生時期はシスト(休眠胞子)の状態で海底に存在している。水温が適当になると目を覚まして
栄養細胞として増殖し、カキ、アサリ、ムラサキイガイなどの二枚貝が栄養細胞を餌として体内
に取り込み毒化する。アレキサンドリウム属の一部では現場水温が発生を知る良い指標とな
るが、ギムノディニウム カテナータムは真夏から真冬まで発生するので水温による予測が困
難である。また下痢性貝毒の原因プランクトンはシストを形成しないため、専ら栄養細胞のモ
ニタリングによって貝毒発生を予測せねばならない。
有毒プランクトンを含む植物プランクトンの増殖には、先に述べた水温の他に、潮流、塩分、
光強度、風などの物理的要因、栄養塩濃度などの物理化学的要因、他の生物による捕食など
の生物的要因など、様々な要因が複雑に関係しており、環境要因から単純に発生を予知する
ことは困難を極める。ただ一般的に海水交換率の低い内湾で、底質が悪化している(例えば
ヘドロの堆積など)場所では、有毒プランクトンのシストが蓄積し易いので、潜在的に貝毒発生
の危険が高いと言える。そのような海域では以下に述べるような調査と検査体制を整えて貝毒
発生を未然に予測することが重要である。
光強度、風などの物理的要因、栄養塩濃度などの物理化学的要因、他の生物による捕食など
の生物的要因など、様々な要因が複雑に関係しており、環境要因から単純に発生を予知する
ことは困難を極める。ただ一般的に海水交換率の低い内湾で、底質が悪化している(例えば
ヘドロの堆積など)場所では、有毒プランクトンのシストが蓄積し易いので、潜在的に貝毒発生
の危険が高いと言える。そのような海域では以下に述べるような調査と検査体制を整えて貝毒
発生を未然に予測することが重要である。
6 原因プランクトン調査および貝毒検査について
貝毒の監視は二重三重の監視機構で行われており、毒化した貝類が市場に出回ることは基
本的にはない。また原因プランクトンの出現から予め貝毒発生を予測する手法も開発されてき
ており、ある日突然貝が毒化して大騒ぎするということは無くなってきた。
本的にはない。また原因プランクトンの出現から予め貝毒発生を予測する手法も開発されてき
ており、ある日突然貝が毒化して大騒ぎするということは無くなってきた。
貝毒の監視は、1)生産現場でのプランクトン出現および出荷前の貝類の毒量監視、2)市場
へ入荷された後の流通段階での毒量監視、3)輸入水産物中の毒量監視の3本柱で行われて
いる。1)については自治体の水産部局が、2)については自治体の衛生部局が、3)について
は国の機関である税関や検疫所が実施している。以下に主たる監視体制である自治体の生
産現場における監視方法の具体例を示す。
へ入荷された後の流通段階での毒量監視、3)輸入水産物中の毒量監視の3本柱で行われて
いる。1)については自治体の水産部局が、2)については自治体の衛生部局が、3)について
は国の機関である税関や検疫所が実施している。以下に主たる監視体制である自治体の生
産現場における監視方法の具体例を示す。
1) プランクトン調査
周年を通じて貝毒の原因となる有毒プランクトンの出現やその密度など発生状況について調
査を実施する。
査を実施する。
2) 貝毒検査
プランクトン調査と同時に当該海域で生産される貝類を対象にマウス毒性試験を行い、毒性
の有無について調査する。
の有無について調査する。
3) 貝毒が検出され、しかも規制値(4MU/g)を越えた時の対応
麻痺性貝毒にあっては、養殖されている貝類から規制値を超える毒素が検出された場合、
自治体を中心に概ね次のような対応が執られる。
自治体を中心に概ね次のような対応が執られる。
4) 生産及び出荷の自主規制
生産者団体(主に漁業協同組合)に対して、生産及び出荷の自主規制を指導する。また、生
産者団体は、生産者に対して自主規制の通知を行うとともに、生産出荷の規制の徹底、漁場
の監視強化、規制への措置状況の報告を指導する。
産者団体は、生産者に対して自主規制の通知を行うとともに、生産出荷の規制の徹底、漁場
の監視強化、規制への措置状況の報告を指導する。
5) 広報
生産者以外の者の採捕や摂食(遊魚者による自家消費)による事故防止のため、広報を行
いその周知に努める。
いその周知に努める。
6) 生産出荷の再開
麻痺性貝毒および下痢性貝毒のいずれも毒性が不検出(ND)になったことを確認した後、行
政及び研究機関の判定会議を経て、食品としての安全性を確認し消費者団体、生産者団体、
流通及び加工関係者等に通知する。また、生産者団体は通知を受けた場合、自主規制等を
解除し、速やかに生産者、流通及び加工関係者等に通知する。また、判定会議で安全が確認
された場合、広報を行いその周知に努める。
政及び研究機関の判定会議を経て、食品としての安全性を確認し消費者団体、生産者団体、
流通及び加工関係者等に通知する。また、生産者団体は通知を受けた場合、自主規制等を
解除し、速やかに生産者、流通及び加工関係者等に通知する。また、判定会議で安全が確認
された場合、広報を行いその周知に努める。
7 貝毒発生による被害対策
貝毒による被害防止策としては、貝毒発生予知技術の開発、原因有毒プランクトンの殺滅技
術の開発、汚染された貝の解毒法の開発などが考えられる。
術の開発、汚染された貝の解毒法の開発などが考えられる。
1) 貝毒発生予知技術の開発
アレキサンドリウム属は毎年、冬から春にかけて増加する。シストの発芽や栄養細胞に直接
影響する水温は予知指標として有効である。従って、予め貝毒が発生する時期に生産を控
え、プランクトンの発生が終息したら生産を再開することで汚染された貝類を処分することが回
避できる。しかし、海域によって海況条件は大きく異なること、むやみに生産を抑制すると経済
活動に悪影響を及ぼすことから、海域ごとに環境要因と細胞の変遷を詳細に監視することに
より予知技術の精度を高めていく必要がある。
影響する水温は予知指標として有効である。従って、予め貝毒が発生する時期に生産を控
え、プランクトンの発生が終息したら生産を再開することで汚染された貝類を処分することが回
避できる。しかし、海域によって海況条件は大きく異なること、むやみに生産を抑制すると経済
活動に悪影響を及ぼすことから、海域ごとに環境要因と細胞の変遷を詳細に監視することに
より予知技術の精度を高めていく必要がある。
2) プランクトン殺滅もしくは発芽抑制法の開発
有毒プランクトンの細胞を崩壊させるには、たとえ有効かつ適切な薬剤もしくは化合物が見
つかったとしても、広い海域に効力を発揮させるだけの量を散布することは困難であるし、生
態系への影響が問題となると予想される。従って現実にはこれらの殺滅技術の開発は進んで
いない。有毒プランクトンの多くはシストを形成し発芽条件が整うまで海底に休眠するため、覆
砂など海底の被覆によりシストの発芽防止を行う方法も考えられるが、対象面積が広大なこと
とコストの問題があり、その実施は困難が予想される。
つかったとしても、広い海域に効力を発揮させるだけの量を散布することは困難であるし、生
態系への影響が問題となると予想される。従って現実にはこれらの殺滅技術の開発は進んで
いない。有毒プランクトンの多くはシストを形成し発芽条件が整うまで海底に休眠するため、覆
砂など海底の被覆によりシストの発芽防止を行う方法も考えられるが、対象面積が広大なこと
とコストの問題があり、その実施は困難が予想される。
3) 解毒法の開発
麻痺性および下痢性貝毒のいずれも毒力は加熱による変化はないと考えられている。しか
し、一部の貝では生きた状態でオゾンや紫外線照射海水中で飼育することで解毒が進行する
という報告もある。また、毒の大部分は中腸腺に蓄積されているのでこの部位をホタテガイ、ヒ
オウギガイ、アカザラガイのように簡便に除去することが可能であれば毒力を低下させること
が可能であり、ホタテガイにおいては実際に有毒部位を除去して出荷する手法も認められてい
る。しかし有毒部位を除去できないマガキやアサリなどではこうした手法は不可能である。現
在のところ、ホタテガイの有毒部位の除去を除き、コストや技術的な問題から解毒法の開発は
ほとんど実践されていない。
し、一部の貝では生きた状態でオゾンや紫外線照射海水中で飼育することで解毒が進行する
という報告もある。また、毒の大部分は中腸腺に蓄積されているのでこの部位をホタテガイ、ヒ
オウギガイ、アカザラガイのように簡便に除去することが可能であれば毒力を低下させること
が可能であり、ホタテガイにおいては実際に有毒部位を除去して出荷する手法も認められてい
る。しかし有毒部位を除去できないマガキやアサリなどではこうした手法は不可能である。現
在のところ、ホタテガイの有毒部位の除去を除き、コストや技術的な問題から解毒法の開発は
ほとんど実践されていない。
4) 風評被害の防止
貝毒の発生は食品衛生上の問題として毒化した貝類の出荷を極力控えることが対策の中心
となっているが、生産業者からみた場合、毒化した貝の廃棄や出荷停止による生産活動の阻
害に伴う損失(漁業被害)は深刻である。さらにそれよりも大きな問題として、当該海域の水産
物の買い控えと価格下落などによる風評被害が指摘されている。風評被害の恐ろしさは、例
えば所沢ダイオキシン汚染報道、東海村の臨界事故時の野菜の買い控え、ノロウイルス流行
によるマガキの価格下落などが知られている。
となっているが、生産業者からみた場合、毒化した貝の廃棄や出荷停止による生産活動の阻
害に伴う損失(漁業被害)は深刻である。さらにそれよりも大きな問題として、当該海域の水産
物の買い控えと価格下落などによる風評被害が指摘されている。風評被害の恐ろしさは、例
えば所沢ダイオキシン汚染報道、東海村の臨界事故時の野菜の買い控え、ノロウイルス流行
によるマガキの価格下落などが知られている。
生産者や行政はこうした風評被害を恐れて情報を秘匿しがちであるが、もしそうした状況で
仮に食中毒患者が発生した場合、その地域の生産物に対する信頼は失墜し、ほぼ半永久的
に信頼回復を得ることが困難である。
仮に食中毒患者が発生した場合、その地域の生産物に対する信頼は失墜し、ほぼ半永久的
に信頼回復を得ることが困難である。
いずれにしても、風評被害は消費者の誤解や思い込み、伝達者の説明不足によって引き起
こされるものであり、その事自体は完全なる「人災」である。こうした風評被害を防止するに
は、とにかく広報・啓蒙活動を徹底して正しい知識に基づいた理解と行動を求めていくしかな
い。風評被害を恐れ、情報を「秘匿」すると、逆に科学的根拠のない噂を一人歩きさせ、これ
が啓蒙活動の最大の妨げになるので、中長期的には百害あって一利なしである。
こされるものであり、その事自体は完全なる「人災」である。こうした風評被害を防止するに
は、とにかく広報・啓蒙活動を徹底して正しい知識に基づいた理解と行動を求めていくしかな
い。風評被害を恐れ、情報を「秘匿」すると、逆に科学的根拠のない噂を一人歩きさせ、これ
が啓蒙活動の最大の妨げになるので、中長期的には百害あって一利なしである。
|

